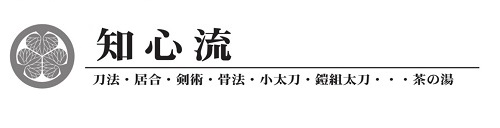Q. どのような稽古ですか?また習得にどのくらい時間がかかりますか?
A. 身体を無理なく楽に動かすことを念頭に置いて稽古します。それぞれの体力に合わせた稽古方法がありますが、先ずは最初に「呼吸法」の習得を目指します。併せて武士の歩き方や立ち居振る舞いなどの基本所作を学んだ後に剣術の稽古に入ります。剣術の稽古は木刀で行い、しばらくして居合刀(模造刀)での稽古が始まります。稽古を積んでいくと木刀での立会稽古が始まります。高段者には約束もなく自由に相手と立ち会う「自由組太刀」(乱取り)の稽古もあります。
以下、中堅門下生の例で紹介します。
入会時:武士の歩き方や立ち居振る舞い、呼吸法などの基本動作の習得。
2 ヵ月後:入門許可。木刀での稽古。面斬を中心に基本的な稽古。
半年後:木刀で寸止めの稽古。合わせて袈裟斬りなどの基本の応用。
一年後:居合刀(模擬刀)を使っての抜刀納刀の稽古。
三年後:初許し認可。刀の形を稽古。同時に木刀での立会稽古。
五年後:初伝を取得(黒帯)。真剣の使用、試斬り、などの稽古。
七年後:中許しを認可。鎧による組太刀の稽古。木刀自由組太刀。
十年後:中伝、奥伝、………。
Q. 武道経験は必要ですか?また年齢制限はありますか?
A. 必要ありません。江戸時代の侍の子弟が元服(15 歳位) になってから始める稽古です。現代では高校生( 男女とも) ぐらいから年齢上限はありません。体力に自信のない方や高齢者も多くいます。侍は何時でも戦えることが使命です。そのための養生法、呼吸法などで、個人個人に向き合い体力にあわせて稽古します。また既に武道の経験者も大丈夫です。ただし他流と並行しての入門はご遠慮ください。
Q. 稽古を始めると、費用は何にどれくらかかりますか?
A. 平均的な例で紹介します( 令和元年現在)。
入会時:入会金5,000、会費8,000 合計13,000 円
(会費は月末に翌月分を納入)
稽古着(胴着、袴、帯、足袋など)約25,000 円~
1 ヵ月後:木刀代(知心流木刀の大小)9,000 円
一年後:居合刀(模擬刀/ しばらくお貸しします)30,000 円~
三年後:初許し免状交付料・登録料・審査料、合計15,000 円
五年後:初伝(黒帯)交付料・登録・審査料、合計26,000 円
Q. 剣術、居合、刀法、小太刀などどの段階で習えますか?また骨法とはどんなものですか?
A. 武家の子弟が侍になるために、元服前から始めるのが木刀剣術です。現代でも同じく、木刀で刀のさばき方を習得して、立合いを経験していきます。その後、実戦に向けて、初めて刃引き刀( 現代では模擬刀) を使います。ここでの抜刀・納刀の基本に続き、居合の形や考え方の教えがあります。刀法とは、矜持(誇り) など武家の道徳であり、剣術・居合など全般を通して伝えます。小太刀を指すのは、武家であることの証であり、その稽古は初伝以降になります。骨法は武士が刀を失った場合や、甲冑武者に対して戦う方法として残されています。